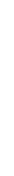2025年8月26~28日に、台湾にて開催された第8回アジア産業衛生ネットワーク学会(以下、ANOH※https://www.anoh2025.tw/)に参加しました。演題は、基調講演2,教育講演6、パネルディスカッション1、口頭発表24、ポスター発表75と大変多くの発表がありました。日本からの参加者は18名でした。
イベントのハイライト動画はこちら
※ANOHとは、Asian Network of Occupational Hygiene (アジア産業衛生ネットワーク学会) の略で、「エイノー」と読みます。学会参加対象者は、産業衛生技術に関わる方や、作業環境測定士、衛生管理者、衛生工学衛生管理者、労働衛生コンサルタント、労働安全コンサルタント、産業医、産業看護職など。学会の目的は、「世界の工場」となっているアジア地域の産業衛生の向上や、ハイジニストの技術・知識の充実、途上国の支援です。
 左から、ANOH立上げに多大な貢献をされたドウ・ヨン・パーク前ANOH理事長(韓国)。ロー・ティ・リン教授(台湾)、中家隆博氏(関西環境科学株式会社)、橋本晴男氏(橋本安全衛生コンサルタント合同会社)、基調講演をされた森晃爾教授(産業医科大学)、筆者(株式会社環境管理センター)、小島謙太郎氏(柴田科学株式会社)、安田知恵氏(関西環境科学株式会社)、柴田優氏(柴田科学株式会社)、現ANOH理事長フィリップ・ヒブス現ANOH理事長(オーストラリア)、中原浩彦氏(NAOSHコンサルティング)。上記写真以外にも、多数の日本人が参加。
左から、ANOH立上げに多大な貢献をされたドウ・ヨン・パーク前ANOH理事長(韓国)。ロー・ティ・リン教授(台湾)、中家隆博氏(関西環境科学株式会社)、橋本晴男氏(橋本安全衛生コンサルタント合同会社)、基調講演をされた森晃爾教授(産業医科大学)、筆者(株式会社環境管理センター)、小島謙太郎氏(柴田科学株式会社)、安田知恵氏(関西環境科学株式会社)、柴田優氏(柴田科学株式会社)、現ANOH理事長フィリップ・ヒブス現ANOH理事長(オーストラリア)、中原浩彦氏(NAOSHコンサルティング)。上記写真以外にも、多数の日本人が参加。
筆者は、今回は「災害時における児童の有害物質ばく露防を目的としたマスクの選択と着用教育」の演題で発表を行いました。3M(呼吸用保護具の製造メーカー)のパタックさんや、韓国産業安全公団のカンさん、またマレーシアのイジー教授から質問とコメントを頂きました。

今回、ANOHで回議論された中で、いくつかの発表で共通して述べられていたことは「化学物質管理において現在の課題は、非定常作業の増加、低濃度ばく露、非定常時における高濃度ばく露。必要とされる技術は、継続的なモニタリング、リアルタイムモニタリング。今後の重要な技術として、センサー技術、ビッグデータ解析。今まではバラバラだった、個人ばく露測定のリアルタイムデータ、作業時間、作業位置、作業内容の動画、音などを一つにまとめるツールが必要」でした。
日本においても、同じ課題を感じますが、アジアでも同様の課題を感じていて、対策のための新しい技術開発が望まれていました。日本の技術で、アジアが求めているようなアプリなど提供できないかと考えてしまいます。
以下、学会2日間での日本人参加者の様子を、写真にて紹介させて頂きます。

 来年は、2026年9月にモンゴル ウランバートルにて開催予定です。
来年は、2026年9月にモンゴル ウランバートルにて開催予定です。
ぜひ、アジアの産業衛生の熱気を感じに来て頂けると幸いです。
(基盤整備・研究開発室 飯田裕貴子)