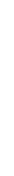私たちは普段何気なく「お米」と呼んでいますが、その一方で、「イネ(稲)」とも呼ばれることもあります。この違いをご存じでしょうか?
簡単に説明すると、「イネ」は水田などで栽培されている植物そのものを指し、「お米」はイネの穂から採れる種子(収穫物)のことを指します。

さて、お米・イネには様々な種類があることをご存知でしょうか?
世界で栽培されているイネは、大きく分けて「サティバ種(Oryza sativa)」と「グラベリマ種(Oryza glaberrima)」の2種類です。
サティバ種は、アジアで広く栽培されているもので、さらにジャポニカとインディカに分けることができます。日本で一般的に食べられているお米はサティバ種のジャポニカとなります。粒の形や食感、香りなど様々な特徴があり、「うりぼーに知ってほしい世界 お米の世界編」でうりぼーにも試食してもらった4種類のお米も、このサティバ種になります。
一方、グラベリマ種はアフリカで広く栽培されていて、サティバ種に比べて収量は少ないですが、環境ストレスや病害虫に強いのが特徴です(参考情報1)。
近年は、アフリカの食糧問題解決を目指して、収量の高いサティバ種とストレスや病害虫に強いグラベリマ種を交配した「ネリカ(NERICA: New Rice for Africa)」も育成されています(参考情報1,2)。
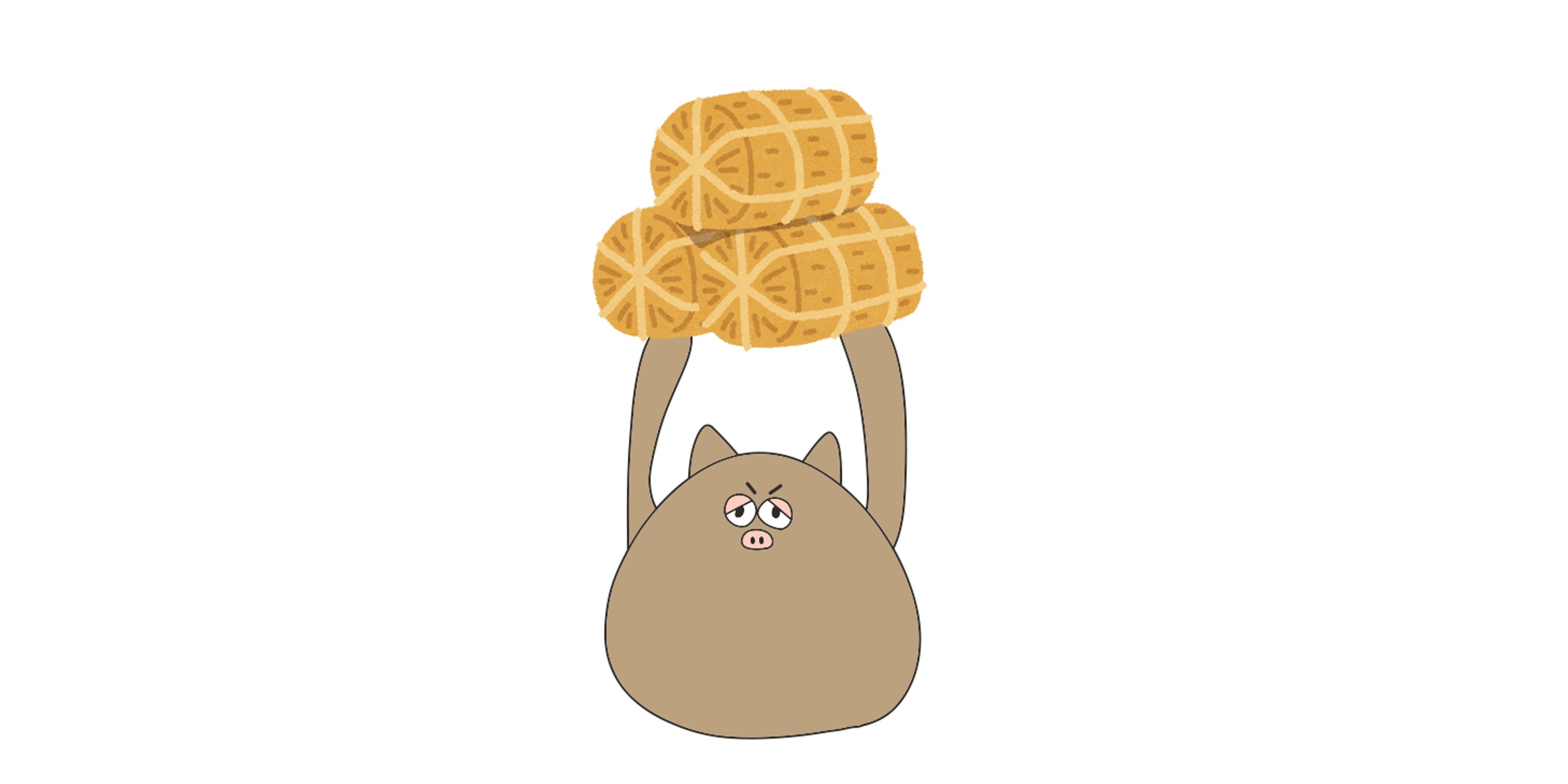
お米には白米だけでなく、紫黒米や赤米など、色がついたお米も存在します(参考情報3)。紫黒米は、アントシアニン系の色素を含み、紫〜黒色をしており、黒米、紫米とも呼ばれています。昔の中国では皇帝に捧げる薬膳米として扱われていた歴史もあります。赤米は、タンニン系の色素を含み、赤褐色をしています。一説では、赤飯のルーツではないかとも言われています。また、紫黒米や赤米の色は、精米することで色が落ちたり薄くなったりします。さらに、緑米と呼ばれるものもあり、これはクロロフィルという色素を含みます。これらは、白米とは違った味わいや栄養価を持っており、最近では「古代米」として売られている場面も見かけます。
栽培方法によっても、大きく「水稲」と「陸稲」に分けることができます。
水稲は、水田に水を張って栽培されるイネで、日本を含む多くの国で一般的に栽培されています。水田は、雑草の抑制や養分供給、温度管理などに役立ち、安定した収量を得やすいのが特徴です。
陸稲は、畑で水を張らずに栽培するイネで、水田が利用できない地域、雨の少ない地域で栽培されています。乾燥に強く、栽培期間が短い品種が多いのが特徴です。
また、国内での栽培を見ることはまずありませんが、世界には「浮イネ」と呼ばれるものもあります。東南アジアのある地域では、雨季になると洪水が頻繁に起こるため、通常の水稲栽培ができません。しかし、このイネは水位に合わせて茎が長く伸び、成長するため、洪水でも水没などしないよう適応したイネです(参考情報4)。
このように、お米・イネには様々な種類があり、それぞれに特徴があります。 私たちが普段食べているお米も、その多様性の中の一つに過ぎません。
他にも色々なお米・イネがまだまだ沢山あります。お米・イネの種類や栽培方法について知ることで、より深くお米・イネの魅力を感じることができるのではないでしょうか。(執筆:春原)
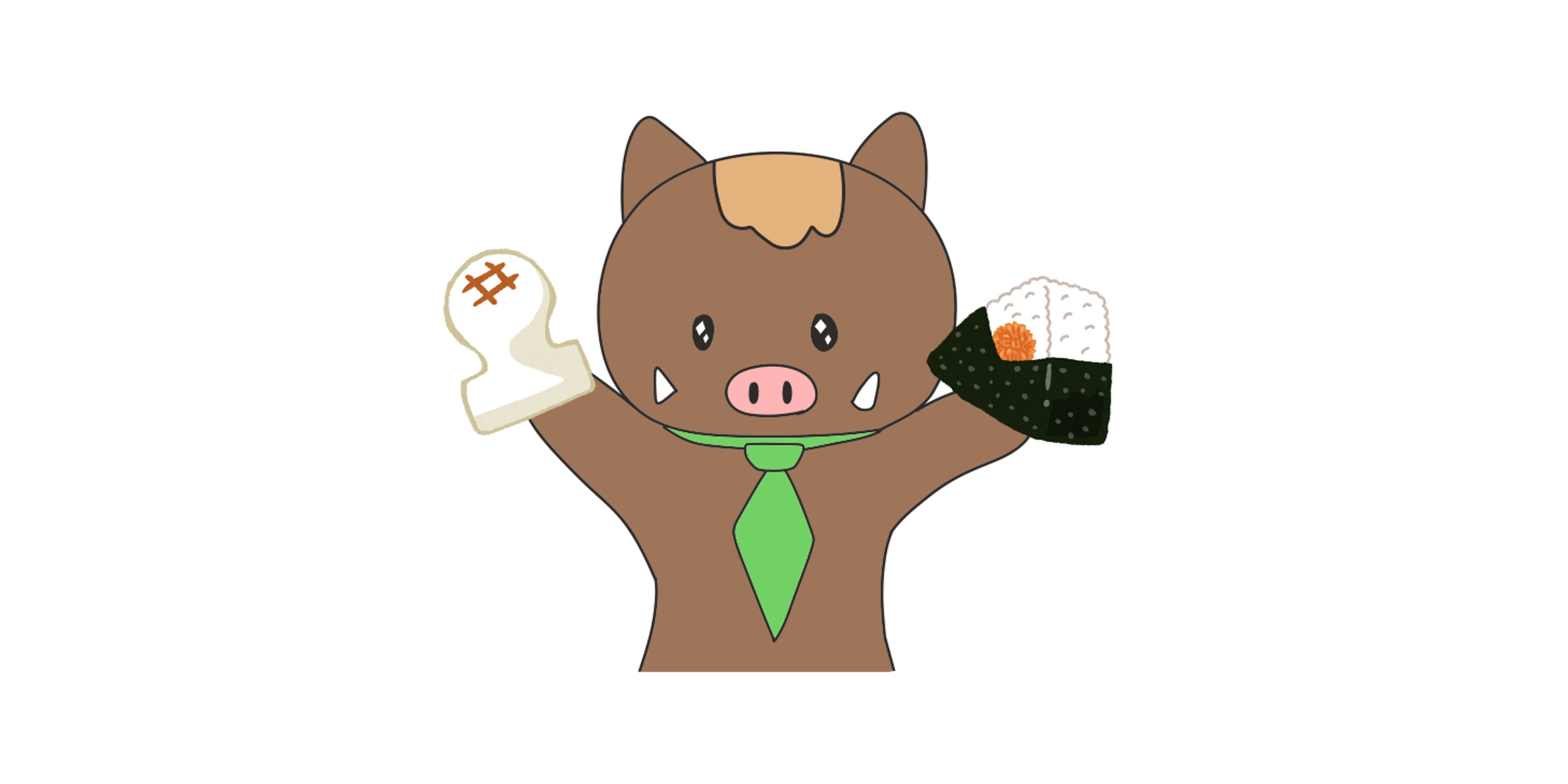
【参考情報】
1)石井龍一 (2003) イネはアフリカを救えるのか? 熱帯農業 47巻5号 332-338
2)ネリカ(NERICA):https://www.jica.go.jp/activities/issues/agricul/approach/nerica.html
3)猪谷富雄 (2012) 「古代米」から稲の世界へ 日本醸造協会誌107巻10号 719-732
4)菅洋 (1988) 浮稲の生物学 植物の化学調節 23巻2号 131-141